新卒採用で人材を募集していてもなかなか応募が集まらない。という問題に直面したことはありませんか?
この記事では中小企業の経営者・採用担当者に役立つ、採用成功につながるポイントをお届けします。
社員を採用しようとするとき、できるだけ多くの人材に応募してもらうことが大切になります。
しかし応募者を集めるにはまず、社員を募集していることを知ってもらわなければなりません。
この社員を募集していることを知っていて応募してくれる可能性のある集団を「母集団」といい、母集団をつくりだすことを「母集団形成」といいます。
「母集団を多くする」、ごく一部の有名企業では難しいことではないのかもしれませんが、そうでない場合はどうしたらいいのでしょうか?
「母集団形成」について、十数年にわたって新卒、中途採用のプロジェクトを担っている社会保険労務士資格をもつ現役人事部管理職が、採用する企業目線で採用初心者からべテラン人事担当者にまで役にたつ方法を解説します。
採用の最初の関門「母集団形成」
「母集団」という言葉は日常で使うことはあまり多くはないかもしれませんが、「採用」ではとても重要なことになります。
「採用」では「自社に応募してくれる可能性がある応募者の集団」を母集団と呼んでいます。
「採用」では、自分の会社が人材を募集していることを知っている人の中から応募者がきます。
採用していることを知っている人全員が応募してくれる訳ではないので、母集団の中の一部が応募してくれます。
そこから書類選考、面接・GW(グループワーク)、適性検査(SPI、RST等)、BG(バックグランドチェック)、最終面接等の段階を経て絞り込まれます。
| 母集団 (通過率) | 応募
10% | 書類選考
20% | 面接・GW
50% | 適性検査
50% | BG
40% | 最終面接
50% | 内定 |
| 10,000 | 1,000 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 10 |
| 1,000 | 100 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 |
このように母集団の数がダイレクトに内定数に直結します。
「母集団形成」の”質”も大切
いかに母集団が多くなっても、求めている人物像(ペルソナ)とかけ離れた人が集まっても最終的に内定を出せる人は少なくなるでしょう。
このため、母集団を形成するときには“数”と”質”がとても重要になります。
いかに求める人物像(ペルソナ)にマッチした母集団を多くするかが採用のカギとなるのです。
実は23卒の母集団形成が調子悪めです。どうも当社の情報まで辿りついてない印象。アクセス数や開封数が少なめです。辿り着いた学生さんのエントリーは悪くないのでリーチの仕方に課題がありそう。昨年とアプローチ変えてないのに何でだろ??
— へび@人事(採用、教育、配置)+総務 (@hebikazuhiro) December 13, 2021
このような悩みを抱えてはいないですか?
では、どのようにして母集団形成するかを説明します。
新卒採用における「母集団形成」を増やす方法は?
新卒採用で厚い母集団を形成するための第一歩は求める人物像(ペルソナ)を具体的に定めることです。
新卒採用は特定の職種の人材を求める以外は入社後に育成していくケースが多いので、性格や人柄など属人的な要素のウエイトが大きくなります。
ペルソナ設定で大切なことは、人事担当だけで考えずに各部門長や現場のリーダーから意見を十分にヒアリングすることです。
採用を全社のプロジェクトとして共有することで、よりペルソナがニーズに合ったものになり、採用の各段階において協力が得られやすくなります。
こうして導き出した「求める人物像(ペルソナ)」にそって「募集要項」を定めて母集団形成のアプローチをしていきます。
では、新卒採用で母集団形成の方法を解説します。
新卒採用で「母集団形成」を増やす方法
主な手法です。
1.就職サイト (マイナビ、リクナビ等 学生が登録する)
2.ダイレクトリクルーティング(学生にむけて企業からアプローチする)
3.合同会社説明会(就職サイトや自治体などが開催する説明会に出展する)
4.学内会社説明会(大学などが開催、多くは大学側が出展企業を選択する)
5.自社HP(公式掲示板、正確に情報を掲載)
6.インターンシップ(就業体験を開催する)
7.学校の就職課(キャリアセンター)に求人を出す(無料で利用可能)
8.若者ハローワーク(応募者は多種多様)
9.SNSでの発信(X(旧ツイッター)は訴求力高い)
どれも一長一短です。
企業規模、知名度、地域、業種、求める人物像、採用時期などで選択肢が決まってきます。
「母集団形成」筆者の会社では
筆者の会社での母集団形成方法を解説します。
筆者の会社は地方の大手企業で地域における知名度はトップクラスです。
求める人物像(ペルソナ)を簡単に述べると、中堅大学以上の大卒で地方就職志向があり、広い職種をこなせる応用力と柔軟性のある人材です。
このため、新卒大学生の多くが登録する1の就職サイトを母集団形成の中心に据えています。また就職サイトでも地方に特化した事業者もありますので併用しています。
地方での就職を目指す学生の多くには会社名を知ってもらっている可能性が高く、少なからず興味を持っている学生が存在することが想定されるので、入口をしっかり確保することが重要だからです。
これに加えて3、4、5、6、7、9を加えていますが、さらに知名度を上げる、優秀な大学の学生にアプローチする、インターンシップで有望な学生を青田刈りするためです。
特に9はX(旧ツイッター)の公式アカウントで細かく発信しています。
採用情報だけでなく、企業トピックスや、採用担当者の日記的なものまで発信しています。
企業の雰囲気や採用担当者の人柄、企業カラーが伝わり、会社への親和性が高まるからです。
3は学生のなかでの自分の会社がどのような位置づけなのか、そして学生が企業に求めるものは何なのかを知ることができます。
学生との接触を多くして、学生が求める形で求める情報を発信することが母集団の質を高めることにつながります。
4は学生への訴求効果は高いのですが大学に選ばれる必要があります。
よほど知名度の高い企業や、継続して卒業生を採用している企業であれば、大学から声がかかりますが、そうでない場合は、足繫く大学のキャリアセンターに通って担当者との顔つなぎが必要になります。
5は必要な情報を正しく載せていくという意味で有効です。
新卒学生は有給休暇取得率、育休取得率などの福利厚生面と、入社後1年以内、3年以内の具体的キャリアパスの関心が高いので、偽りなく、わかりやすく伝えるようにしています。
ほかの手法で知名度をあげて、そのうえでHPに誘導していくことが大切です。
7は募集要項は主な社員の出身大学に送ります。
2はコピペ文章のメッセージを送っても効果は薄いので、これぞ、という人にオリジナル文章を送らなければなりませんが、それでも100発撃って1発あたればいい、くらいの確率になります。
8は試したことがありますが、希望する人物像の学生はなかなか紹介されなかった印象です。
以上が新卒向けの母集団形成を増やす方法です。
企業によって使うべき選択肢は違いますので、トライアルをくりかえして自社にあった方法をみつけてください。
質問があればコメントを残してください。
質問への回答の記事を書いていきます。
これまでは自社の採用活動の母集団形成は人事だけでやっていたのを、事業部メンバーにも協力してもらう形に運用改善しているのですが、事業部側の行動だけで従前に近い感じの母集団形成ができるようになってきておりまして、協力しながらも任せるところは任せるのってホントに大事だなと思いました。
— 長澤 成啓@TOWNの人事 (@seenagasawa) May 6, 2021
新卒採用の「母集団形成」におけるインターンシップの役割
6のインターンシップは工数がかかる作業ですが、想定する参加人数が確保できれば母集団形成に役立ちます。
インターンシップ(就業体験)は企業側にすれば、仕事を体験してもらうことで採用のミスマッチを減らすことができて、人柄やスキルも知ることができる機会になります。
参加者は半日や一日を費やすことになるので、意識が高い学生が来てくれます。
学生側からすれば、会社の雰囲気や社員像を自分の目でみて確認できますし、入社後に担う仕事のイメージがつきやすくなるので応募する学生の親和性も高まります。
参加者を集めるには大学等でインターンシップ開催情報を掲載してもらうか、1でインターンシップ情報を発信します。
しかし確実に学生に訴求していないと、せっかく開催しても参加者が想定よりも大幅に下回ることがあります。
実施しても学生の満足度を上げないと逆効果になりますので入念な準備が必要になります。
ただPPTを見せて説明するのではなく、具体的に手を動かす作業をすること、人事担当者以外の社員と交流すること、企業トップと参加者が話す場を設けると効果的です。
手間はかかりますが、成功すれば効果が高い手法です。
「母集団形成」を増やす方法 まとめ
1 求める人物像の設定がなによりも大切
2 求める人物像、企業によって、効果的な手法は様々
3 中途採用は新卒以上にキャリアパスの明確化、待遇の整備が重
最後まで読んでいただきありがとうございます。
解説してほしい内容や質問があれな、コメントを残していただければ、回答していきます。



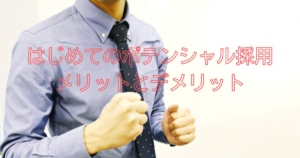
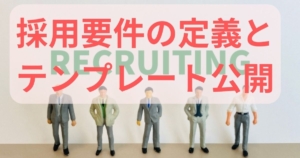


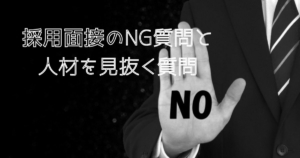

コメント
コメント一覧 (13件)
[…] 募集要項がしっかり定まると、採用の前段階になる「母集団形成」にもつながります。 […]
[…] 自社をよく知る社員が候補者を紹介するため対象者の企業への理解が深まり、母集団形成の段階で人材の質が高くなります。 […]
[…] 集まり、採用での母集団形成にも役立ちます。 […]
[…] 募集要項を定めるときは、必要な要件を満たしながらも社が必要な人物像をどう落とし込めばいいか、実際に募集要項を公開しても、母集団形成がうまくすすまないなどの課題や疑問に直面し感じることが多々あります。 […]
[…] 説明会の参加者が増えれば母集団形成に役立ちます!母集団形成のポイントはここ! […]
[…] 優秀な人材獲得に必要な母集団形成のポイントはここ […]
[…] 採用で悩む「母集団形成」とは?増やすにはどうしたら?中途採用ではどうする? […]
[…] 採用で悩む「母集団形成」とは?増やすにはどうしたら?中途採用ではどうする? […]
Hi! Quick question that’s completely off topic. Do you know how
to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone 4.
I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix
this issue. If you have any suggestions, please share.
Thank you!
[…] リファラル採用のポイントとデメリット、報酬の相場とトラブル回避方法 […]
[…] 採用で悩む「母集団形成」とは?増やすにはどうしたら?中途採用ではどうする? […]
[…] 採用で悩む「母集団形成」とは?増やすにはどうしたら?中途採用ではどうする? […]
[…] 採用で悩む「母集団形成」とは?増やすにはどうしたら?中途採用ではどうする? […]