毎年1000人以上の就活生と接していて、近年は特に「福利厚生」を重視する傾向が強くなっていると感じています。
一昔前では採用担当者に「福利厚生」について質問するのも憚られる空気がありましたが、むしろ今は逆で積極的に「福利厚生」について聞かれますし、企業側から「福利厚生」に時間を割いて説明することが求められています。
この記事では企業側からすれば優秀な学生を多く集めるポイントになり、就活生からすれば企業選びの重要な要素となる「福利厚生」を10年以上新卒採用と中途採用を担当している社会保険労務士資格を持つ大手企業の人事部管理職が企業と就活生のそれぞれの視点で解説します。
企業に義務付けられている法定福利厚生費とは

「法定福利厚生費」とは、健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料などの社会保険料や子育て拠出金、また、雇用保険料、労災保険料などの労働保険料です。
法律で会社が負担を義務付けられている社会保険や労働保険の保険料のことを指します。
社会保険や労働保険のうち雇用保険の保険料は法律で会社の負担割合が定められていますが、企業によっては健康保険や厚生年金保険の保険料を法定の負担割合よりも多く負担している企業もあります。
あまり目につきにくのですが、法定分を超えた分は社員へのメリットが大きい福利厚生となります。
「法定福利厚生費」は「法定福利費」というのが正しい名称で「福利厚生費」の一部です。

まず企業が社会保険や労働保険にきちんと加入しているかを確認しましょう
法定福利費厚生費① 雇用保険
雇用保険の失業給付は会社を退職した際に受け取れる給付金で、仕事を辞めた場合に当面の生活を支える大切な収入になりますので、雇用保険にしっかり加入しているかを確認しましょう。
雇用保険に加入することで一定の条件を満たせば失業給付が受けられます。
フルタイムで働く場合は雇用保険の対象となりますが、パートの場合は適用外の場合もあります。
パートの雇用保険適用の目安は週の労働時間が20時間以上となります。



雇用保険は失業したときにとても便りになります
法定福利厚生費② 労災保険
業務上の事由や通勤の際のケガや病気に対する保険給付です。
病気やケガの治療費の補償だけでなく休業中の賃金補償もあり、後遺障害がある場合や死亡した場合にも本人やその遺族への保険給付が行われます。
労災保険は企業が加入するので、労働者ごとに加入する必要はありません。
企業選びをする際は企業が労災保険に加入しているかを確認しておきましょう。



通勤時に家の玄関先で転んでも労災の対象です。
法定福利厚生費③ 健康保険
業務外の病気やケガをした際の出費に対し自己負担が軽減されます。
出産育児に対しても一時金が支給されます。
また業務外の病気やケガで働けなくなった場合の手当もあります。
健康保険の加入確認と健康保険の給付内容を確認しましょう。
人事部担当者も制度をいちど再確認しておくと便利な給付制度を発見することもあります。
健康保険の保険料の企業側法定負担割合は50%です。
法定福利費④ 厚生年金保険
公的年金制度のひとつで原則として65歳になると一定の条件を満たせば老齢厚生年金が給付されます。
収入に応じて年金保険料が異なるため、納めた保険料が大きくなれば受給額の大きくなります。。
高い給与の人は年金の額も高額になります。
一定規模以上の企業は厚生年金の加入が義務付けられていますが、まだまだ未加入の企業も多いです。
企業選びの際に厚生年金加入を確認することはとても重要です。
厚生年金保険の企業側の法定負担割合も50%です。
新卒就活で重視すべき福利厚生ランキング ワークライフバランス重視


「法定福利厚生費」以外の「福利厚生」は、企業が従業員の健康維持やモチベーション向上などを目的とした福利厚生制度にかかるお金のことで、給与以外の従業員へのサービスといえます。
企業が独自で定めている福利制度のため、その内容は企業によって大きく異なります。
福利厚生は労働条件の大切な要素なので、制度の充実度を見るには法定外の福利厚生制度をチェックすると良いでしょう。
福利厚生ランキング 1位 住宅手当 扶養家族に支払われる「扶養手当」
社員の生活へのインパクトが大きいのは「住宅手当」と扶養家族がいる場合の「扶養手当」です。
「住宅手当」は生きていくうえで欠かせない「衣食住」のうち「住」の補助になりますので、社員の暮らしへの影響が大きい「福利厚生費」です。
家賃の一部補助または全額を支給したり独身寮や社宅の入居ができる企業もあります。
「扶養手当」は扶養家族について手当を支給します。
扶養家族は簡単にいうと年収が一定の金額以下で従業員の収入で生計の大半を担っている家族で、主に専業主婦や子供たちです。
こうした扶養家族を対象に支給されるのが「扶養手当」になります。
福利厚生ランキング 2位 通勤手当
通勤にかかる交通費の一部または全額を支給します。マイカー通勤でのガソリン代の補助や定期券の現物支給、最寄り駅までのバス送迎なども含まれます。
テレワーク導入企業が増え、通勤手当を廃止しテレワーク費用補助に替える企業もでてきています。
福利厚生ランキング 3位 医療健康
企業には従業員の健康診断の実施が義務付けられています。
法律で定められた健康診断に加え、人間ドックの受診補助、医療費の自己負担分の一部補助や、医療費が高額になった場合の補助などもあります。
また健康保険適用外の自由診療部分への補助などもあります。
健康増進のためのスポーツクラブの利用特典や保養施設を設けている企業もあります。
福利厚生ランキング 4位 休日 新卒の注目度上昇中
法律では一週間に1日以上、4週間で4日以上の休日を付与することが定められています。
これ以上の休日が付与されるのか、付与される場合は何日なのかが大事です。
間違いやすいのは「完全週休二日制」と「週休二日制」です。
「完全週休二日制」は一年を通じて毎週二日の休みが設定されていることです。設定される曜日は土日とは限りません。
「週休二日制」は一年を通じて月に一回以上は週に二日の休みが設定されるということです。隔週で二日の場合もあれば、月に一回の場合もあります。
休暇での重点チェックポイント 有給休暇日数と取得率
有給休暇は法律で付与する日数が定められています。
付与の条件は以下の通りです。
- 使用者は、労働者が(1)6ヶ月間継続勤務し、(2)その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、10日(継続または分割)の有給休暇を与えなければなりません。
- 6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、継続勤務3年6ヶ月以降は2日づつを増加した日数(最高20日)を与えなければなりません。
有給休暇は法律に則って付与されますが、法律を上回る付与日数の場合もありますし実際にどの程度取得しているかが大切です。
募集要項などに書いていない場合は、説明会などで質問しておきましょう。
有給休暇の取得日数は就活生の重大な関心事なので、企業側は取得率を計算して募集要項やHPなどに記載しておきましょう。
取得率が高い場合は、就活生へのアピールポイントになります。
法定の有給休暇以外にも、忌引きや結婚休暇、旅行などで使える年間休暇、さらに一定の事由が発生した場合に給与が減らされることなく休める「特別有給休暇」を設けている起業もあるので要チェックです。



有給休暇の法定有効期限(2年)を超えて積み立てられる企業もあります
福利厚生ランキング 5位 カフェテリアプラン 大手企業は手厚い傾向
導入する企業が増えている福利厚生メニューのひとつです。
社員に一定のポイントが付与され、宿泊施設の利用や旅行代金、資格取得費用、医療費の補助などざまざまなメニューが用意され、自分が使いたいサービスにポイントを使うことができます。
福利厚生へのニーズが多様化してきて、普及してきている福利厚生サービスです。
大手企業では導入が進んでいてメニューも豊富になっています。
採用で重視される福利厚生ランキング まとめ
1 法定福利厚生は地味ですが重点チェックポイントです
2 法定外の福利厚生では手当が生活に直結
3 医療費の補助やカフェテリアプランも要チェック
最後まで読んでいただきありがとうございます。
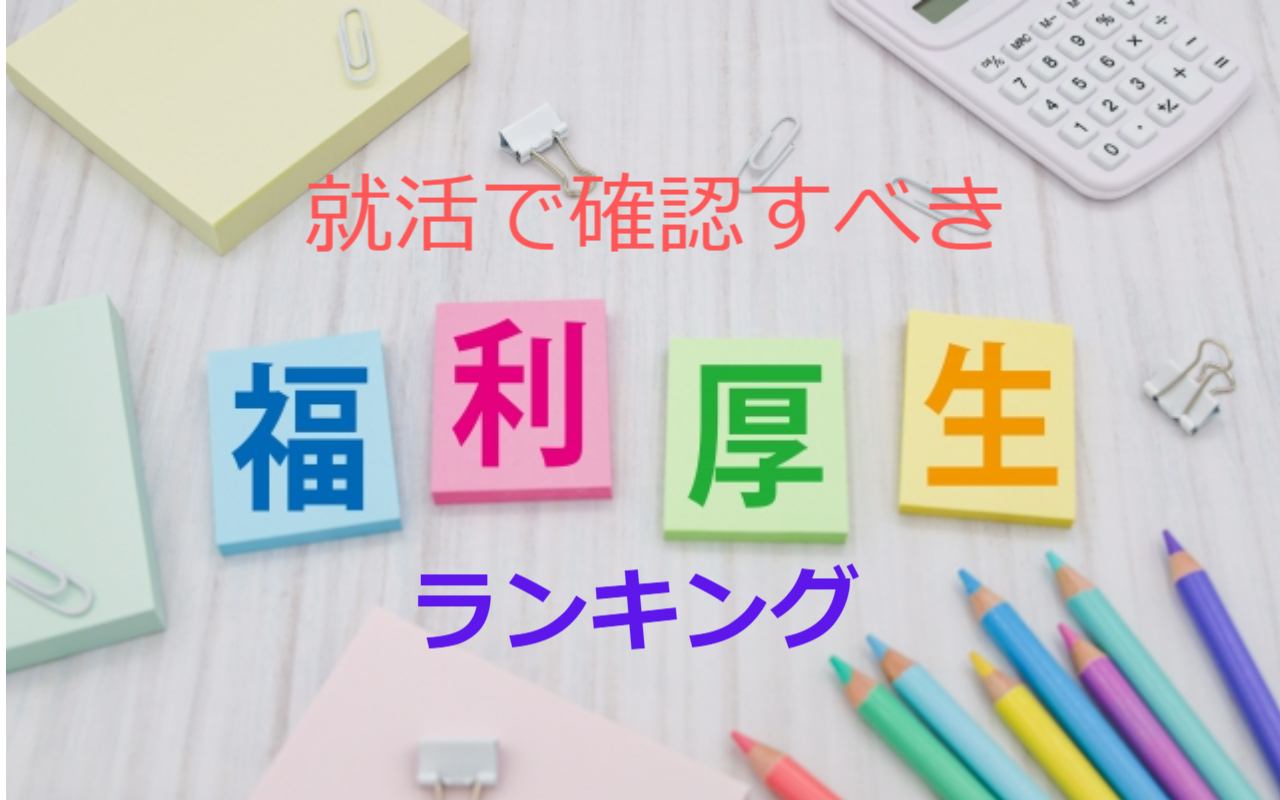


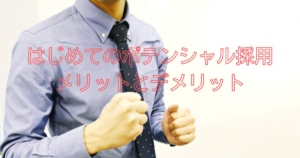
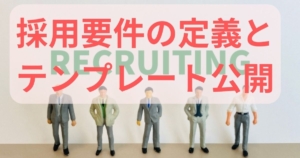


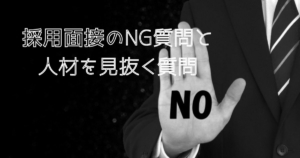

コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 採用で重視される福利厚生で確認すべきことランキング […]
[…] 採用で重視される福利厚生で確認すべきことランキング […]