人事担当者が「リテンション」という言葉を聞くことが増えてきていると思います。
「リテンション」とは「保持」「維持」という意味で、人事担当者が「リテンション」という言葉を使うときは
人材の引き止め、流出防止、離職防止、という意味となります。
経験やスキルを持った人材の離職防止は新たに人材を採用するよりも経営効果は高く、採用と同じかそれ以上に大切な人事施策となります。
人事担当者としては避けることはできない「リテンション」の意味、方法、効果について社会保険労務士資格を持つ大手企業の人事部管理職が現場で得られた経験から解説します。
採用と同効果のリテンション施策(リテンションマネジメント)とは

「リテンション」とは英語「retention」で主に以下の意味があります。
保有、保持、維持、保有力、記憶力
人事部門でリテンションは「人材確保」を意味します。
社員が会社を辞めずに会社にとどまること、そこから派生して優秀な人材や若手・中堅社員などが離職していかない施策を「リテンション施策」と呼びます。
「リテンションマネジメント」といわれることもあります。
リテンション施策がなぜ採用と同じ効果があるのか?
人事セクションではよく「採用が芳しくないのであればリテンション施策を改良して全社で業務遂行力を維持していく」と考えられています。
確かに正しいと思います。
なぜなら新たな人材が入らないのであれば、現有の社員が減ることを防げば総社員数は変わらないからです。
しかし「リテンション施策」がもつ効果はこれだけではありません。
短期的には即戦力として活躍している社員が辞めてすぐには活躍が見込めにくい新入社員が入るのと、リテンション施策が効いて人材の離職率を下げるほうが即戦力が維持されるので、戦力ダウンは低くなります。
長期的には新入社員が入ると新たな発想や経験が獲得されてイノベーションが生まれる可能性が高まりますが、現有社員だけの組織は、発想が硬直化しがちで新しいアイデアが生まれにくくなります。
人事においてリテンション施策は、採用を全て代替するものではないことを理解しておいてください。
リテンション施策の種類
人事の「リテンション施策」の分類として「金銭的リテンション施策」と「非金銭的リテンション施策」に分けられます。
金銭的リテンション施策

金銭的なリテンション施策は、社員に対し賃金や手当、賞与などで与えるお金を増やして離職を防ぐというものです。
【金銭的報酬のリテンション施策の例】
業績連動型賞与支給
成果連動型の昇給
優秀社員への金銭的インセンティブの付与
業績に応じたストックオプションの付与
お金を多く払うことで働くことへの動機づけを促す狙いです。
しかし、短期的には効果がありますが、結果に対する評価が客観性があるものでないと不満が高まります。
私が勤める広告会社でも成果連動型の昇給を導入しています。
業務内容が多岐にわたるので数字で結果が明確に出る職種だけではありません。
成果を客観的に評価するのは困難で、どうしても評価者の主観が強く働きます。
評価者の主観で報酬額が変わるので、一部の高評価が得られた社員以外の不満はたまります。
またより金銭的な報酬を求めて他社への人材流出が加速するケースもあります。
そのため、単純な成果連動型の高報酬リテンション施策だけでは人材流出を止めるには不十分です。
非金銭的リテンション施策

非金銭的リテンション施策のポイントは、社員がやりがいや喜びを感じられる施策を打ち出し、組織への定着を促すことです。
社員が働くにあたって重要視することに「QOL(クオリティ オブ ライフ)」があげられます。
新卒採用の場でも学生が重視する項目に残業時間の多寡や福利厚生が上位に位置しますし、質疑応答でも福利厚生面の質問が多く寄せられます。
私の会社でも客観的に高い成果を上げている社員ほど、キャリアアップ、スキルアップ、働き方のこだわりが強く、単なる金銭的な面だけでは自分の勤務先を選ばない傾向があります。
そのため、昇給やボーナス以外の非金銭的リテンション施策が有効になります。
【非金銭的報酬のリテンションの例】
長時間労働の改善、子育て支援など労働条件の改善
フレックス制やリモートワークといった多様な働き方ができる環境整備
公平で客観的な評価を反映した人事評価制度の見直し
希望の部署に配属するなどのキャリアパス支援
福利厚生・研修・キャリアマネジメントなど、複合的な人事施策を構築することで、社員の会社に対する満足度や帰属意識が向上し、働くうえでのインセンティブが醸成された結果、会社への定着率が高まります。
金銭的リテンション施策と非金銭的リテンション施策を組み合わせることが重要です。
リテンション施策の使い方

リテンション施策を使う場合大事なことがあります。
それはターゲットを明確にすることです。
明確にしたターゲットにどのような目的のリテンション施策を実施するかを定めることです。
なぜなら、社員が会社に求めることはそれぞれで、ターゲット層が大きくなればなるほど最大公約数の施策となり、効率的な施策にならないからです。
リテンション施策の例①
不満を抱える層にワークライフバランスの施策を実施します。
ヒアリングを通じて暮らしと仕事のバランスに不満を抱えている層から具体的な課題を聞き出し、
リモートワークや、フレックスタイム、有給休暇の弾力的な取得方法などの施策を実施します。
リテンション施策の例②
キャリアパスを描きたい層には希望した部署への配置します。
自分が描く未来像を実現するために具体的に支援します。
面談などを通じて社員個人がどのようなキャリアパスを描いているのかを把握し、できるだけ希望に沿った配置をします。
組織全体にかかわることなので、全員の希望を叶えることはできない場合もありますが、希望を聞く場を設けること、いつまでには配置が可能なのかを示し、社員の帰属意識を高めましょう。
リテンション施策と人材定着効果
リテンション施策が効果を発揮すると人材定着効果があります。
社員の組織への帰属意識が高まり働く動機づけが得られます。
そうすると社員の離職は減り人材が定着していきます。
中堅・ベテラン社員が定着しながら、新卒や経験者(中途)を適度に採用すると理想的な人員構成となります。
採用と同じ効果があるリテンション施策 まとめ
1 リテンション施策は短期的には採用以上、長期的には採用と併用
2 リテンション施策には金銭的と非金銭的
3 金銭的と非金銭的を組み合わせて実施するのが大事



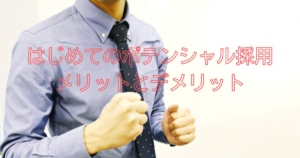
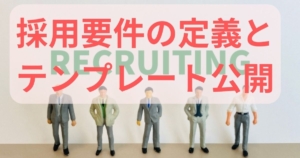


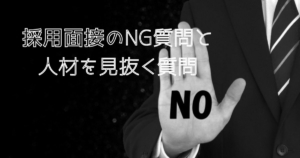

コメント